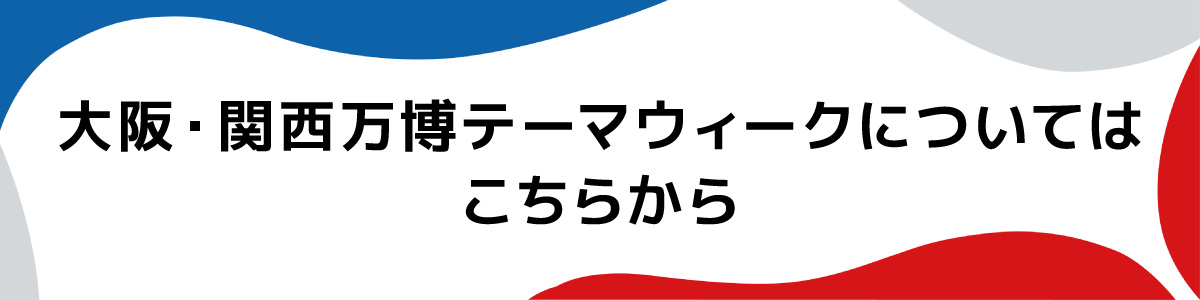公益社団法人2025年日本国際博覧会協会とアジア太平洋トレードセンター株式会社は、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)のテーマウィークの実施に向け、連携協力を行っています。
本WEBページにて、テーマウィークの情報発信を行ってまいります。
10月12日開催のアジェンダ2025 主催プログラムに参加してまいりました。
・開催場所:大阪・関西万博会場内 テーマウィークスタジオ
プログラム①「8人のテーマ事業プロデューサーと考える“いのち”とSDGs+Beyond」



【プログラム概要】
以下リンクよりご確認いただけます。
→8人のテーマ事業プロデューサーと考える“いのち”とSDGs+Beyond
【参加感想】
・将来のSDGs+Beyondへの展望は?
粛々と、現在存在するモノの価値観の相続の追求と進歩し続ける事が寛容かと感じております。継続はチカラ為り。親から子へ、孫への引継ぎ方法に、何かしらの欠落が有る様に思いました。国民の休日は増えましたが、或る一定の期間(短期間でも)何もしない、「無」から遊び始める―原点回帰の時間にする、そのような贅沢な時間の使い方を国民一人一人が見直す、考え直す法案を通して下さい。
MDGsの飢餓をなくす乳幼児死亡率を下げる 妊産婦死亡率を下げる 極度な貧困をなくす学校教育を受けるなど もっと基本的なことを日本の全省庁で作った食育基本法や 旧の栄養改善法を用いるなどして解題解決しようと見受けられない
SDGsは広い範囲をカバーしており、人類が協力して継続して取り組むべき課題とおもいます
オズゲ・アヤドガン氏の提言にあった どの様なジャンル・立場であれ1人1人が自身で出来る範囲でSDGSの取り組みを少しでも良いので意識し積み上げて行くことが大事というシンプルな言葉に胸を打たれた。ジョンレノンの「イマジン」ではありませんが「1人1人が想いを持ち続け 諦めない」ことが大切で これからの世界をより一層変えて行くことになるということに同感しました。
達成するためには、各国のリーダーや旗振り役の役割が重要で、万博やオリンピック等の大きなイベントでギアチェンジして推進して行く必要があると思う。
万博側の意図は分かるけど、共創の場には程遠い。ファシリテーター不在。参加者からの意見の汲み上げも不足していて、共に創る場ではなくPRだけの場になっている。地球規模の課題解決はこの万博の形ではできないと確信を持った。
8人の事業プロデューサーがそれぞれの考えるいのちについて話されてました。気づいたこと分からなかったこともありましたが、今後、将来やいのちについて自分でも考えていきたいと思いたした。ユスリカが大量発生し、それをトンボが食べにきて、またそのトンボを食べにくる鳥や動物が。万博期間中に会場で動的平衡が起こった話しは興味深かった。
8人のテーマ事業プロデューサーのメッセージがしっかり聞くことができたのでこれからの生き方に大変参考になりました。それぞれ異なる使命感や生命感をお持ちの方々ですが、自分自身の考えにフィットしない要素を含めて解釈してこれからの業務を含む「生きる姿勢」に活かしていこうと思います。特に福岡伸一さんの設計的→発生的に意図した「生命の原理にしたがう方向性」が最も共感でき、緑を扱う仕事をしている私にとって大きな示唆を与えて頂きました。ありがとうございます。
万博は、単に各国の文化の発信にとどまることなく、世界の国々が地球的課題であるSDGsをどう理解し、どう解決しようとしているのかを知り、自身の考えや思いと照らし合わせる機会として非常に貴重であった。SDGs++とスライドで表現されていた未来への具体的なロードマップが示されていたと思う。
現状のゴール達成状況を国内、海外を分析してから展望を描く必要がある。上塗りでは、進歩がない。
今後は“目標”としてのSDGsから、“実装・定着”の段階に進むことが重要だと思います。たとえば、環境配慮だけでなく、地域社会のつながりや、次世代に継承できる文化・技術の価値を見直すなど。私たち自身も、製造や販売の現場で無理のないサステナブルな工夫を続けながら、長く愛されるものづくりを通じて、SDGs+Beyondの実現に貢献したいと考えています。
将来のSDGs+Beyondへの展望は?僕としては今回、万博のボランティアをさせていただき、沢山のボランティアが愛を持って取組み、来場者の方々と互いに『ありがとう』を言い合えるボランティア活動は『ありがとう』の向こう側を感じえる素晴らしい取り組みでした
各国の取り組みを通じてSDGs達成に向けた多様な戦略と、その先にある「Beyond」の方向性が具体的に浮かび上がりました。中でもドバイが示した「過去9割+未来1割」の戦略は、既存資産の活用と未来社会の実装を両立する実践的なモデルだと感じました。今後は国家レベルの目標達成にとどまらず、個人や企業、コミュニティ単位での共創を起点とし、多様な価値観を接続することで、新しい社会像を形成していくことが重要なテーマになると思いました。
社会状況、地球環境が変化し続ける中、SDGsの目標達成期間を迎え、過ぎても、各国、各社、各人が、本来持つ独自性を加えた上で、<もったいない>や<他者への感謝(ありがとう)><利他の気持ち>を当たり前のこととして行動し続けるようになっていることこそが、Beyondなのだと思いました。
福岡伸一さんがおっしゃっていたように、ユスリカ大量発生の際、図らずも「動的平衡」が万博会場で実現されていました。私たちが多くの課題に対して、真摯に向き合い、考え、工夫や努力を続けていると、人間の考えの及ばないところでその実現に至ることもあるのだと思います。その意味で、8名それぞれの視点からの取組みのように、私たちも一人一人の視点からの取組みを続けることで、展望は開けていくと思います。
他のプロデューサーがいてくれるおかげで、特定の分野に特化して、取り組めることができた、と言うニュアンスの発言に、周りを見渡しながらバランスをとって、相手の個性の尊重、自分の個性の発揮、そして、足らずはどう補って行くか、リスペクトと考えることを忘れなければ、未来は輝いていくと思います。
日本人の根底に流れる精神の発現として、SDGsがあるのであれば、一定の成果があるとは思う
当日の内容を、万博の開催前・期間中に、もっとアナウンスすべきだったと思います。私も含め、多くの人がSDGs+Beyondという万博の意義を理解している人が少なかったと思います。それが残念でした。
Ⅾがwell-beingのwに変わると、どうなるか。温暖化進行のなか、緊急的にもどうすべきか。
自然界で人間だけがサステナブルではない、だからこそ自分達で考えサステナブルな行動をしなければならない。
未来への文化共創、平和と人権音楽を通じて文化を知り平和を訴えて活動して行きます
EXPO開催の意義・意味について深く考えさせられました。非常に良い内容に感じました。
サーキュラーエコノミー的な観点からは、やはり政府主導でなければ達成しないのではと思っています。仕組み化、ルール運営、水準化を誰もが参加しやすい物にしなければ市民はついていかない。世界が注目する鹿児島県大崎町のように素晴らしいモデレーションが有りながら、一般市民にはあまり知れ渡っていない現状。政府であれ、首長であれ、旗を掲げて主導し自身が実践しなければ、絵空事のように映ってしまう。小さな島国の日本がどれだけ努力しても、全世界が同時に進まなければ、焼け石に水。そもそも、大量消費で潤う資本主義社会に対する革命が求められていない。リサイクル、リユースを市民が一生懸命にやって到達できるのだろうか、と危惧しています。
これから活躍の若い人にはその考えが根付いていくであろうから、新しい発想が期待できる。
万博の中で得た気づきをどう活かすか。展示や体験を通じて、SDGsの理念が「遠い目標」ではなく、「自分ごと」と一人ひとりの心に残っているのではないでしょうか。誰かと一緒に「おいしい!」と笑い合い、「綺麗!」と感動する、その小さな共感こそが、持続可能な未来への第一歩。心が震える体験を共有することで人と人とのつながりが生まれ、世界をより良くしたいという気持ちが自然と芽生えていきます。SDGs+Beyondとは、目標を達成するだけでなく、その先にある「共感」や「創造」を育てること。日常の中でどう活かすかを考え続けることが、未来への種まきになるのだと思います。
プログラム②『「いのち輝く未来社会」のデザインに向けた提言』



【プログラム概要】
以下リンクよりご確認いただけます。
→「いのち輝く未来社会」のデザインに向けた提言 | 大阪・関西万博テーマウィーク
【参加感想】
・SDGsは達成できるか?そして、その先はどうする?
未来への責任の言葉が刺さりました。次に繋がるイメージを持つ発想を持ち、活動したいと感じました。
SDGs有りきの従来の浸透性よりも、発展途上国の論理としての方向付けが大事かと存じます。脱炭素化もそうですし、生産サイクルは決まって主要G7乃至G11の指導の現在を彼ら自身の論理過程を重視するのが、現代に於ける見直しに通じるかと思います。ブランディング化を発展途上国の進捗スピードで考え直しても良い時期に来ているかと思っています。達成不可能な事象を先進国の自然の摂理に反しての金融主義から離れるべきかと思います。
徐々に達成されていくと思います。その後は、新しい技術をつかって、エネルギー効率を高めていく
佐久間氏の「予測し未来に向けて選び取り そして行動したい」という意識の積み重ねがSDGSを達成の可能に出来るのではないか?未来をどのようにするかを意識的に方向づけて行けば達成できるのではないか?その為にも世界の人々の未来を守りたいという「想い」を育んで行くことが大切だと思い自身の業界エンターテインメントを通じて微力ながら貢献できればと感じた。
可能と思う。その為には今のままのアナログ手法ではなく、新しい手法を駆使した、達成に向けた対策や活動に協力してくれる人を増やす必要があると思う。
2030年までに決めた目標を達成するかどうかは、ほとんどの項目で可能性は低いと思う。そしてそもそも持続可能とは、何年間の持続可能性の話をしているのか。まず明確に答えられる人はいない。だって誰も国際社会でもその合意形成をしていないから。だからリサイクルも経済性から後回しになるものが多い。根本から考えた方がいいかも!
現状評価については決して満足できるものではないという見解であったと思うが、万博の貢献度を正確に評価する必要を感じた。専門家や有識者と市民の意識の乖離を埋めるためにはオリンピック、ワールドカップ、エキスポの三大国際イベントを通じた発信や取り組みの促進が不可欠だと思う。
全体的に道半ばと思います。改めて危機感を共有して取り組む必要があると考えます。
全てのSDGsを期限内に達成するのは現実的に難しいと考えています。けれども大事なことは、“世界中が同じ方向を向いた”という事実だと思います。これからは『守る』だけでなく、『創る』——つまり、次の世代に希望をつなぐ新しい仕組みづくりが求められると感じています。
SDGsは達成できるか?そして、その先はどうする?個人が意識を持って取り組み、かつ継続していくことでルールでは無く、潜在意識になって行っていく無意識に取り組む領域に達していくことだと思います
SDGsは、単なる「固定的な目標」ではなく、社会全体の変容を促す「動的なフレームワーク」として捉える視点が重要だと感じました。インドネシアのように自然・文化・テクノロジーを統合的に活用する戦略や、カナダの多様性・文化を軸にした社会変革の姿勢など、各国の実践は多様です。こうした多様な取り組みを有機的に結び付け、継続的にアップデートしていくことで、持続可能な社会を形成していく道が拓けると思いました。
科学技術の進歩は急加速することもままあるので、それに期待すると、達成は不可能ではないと思います。でも、私たちがあきらめたり、投げ出したりすると同様に急加速のスピードで、状況が悪化することも知っているので、本当に私たち人間次第だと思います。SDGsの先は、SWGs(Sustainable Well Being Goals)として、文化や芸術の視点を含む、全ての人のウェルビーイングを目指したい。
達成は簡単ではないですが、達成できると思います。万博では、未来をデザインするには、必要な大事なものを考えさせてくれました。わたしは、物資的にも精神的にも豊かさが大事だと思います。どうすれば豊かになるのか、その問いを考えるのはワクワクしますし、その途中経過にSDGsは達成できて、引き続き考えていると思います。
西洋的な、利己主義、拝金主義が邪魔をするのと同時に、日本に流入する(させようとしている勢力あり)が、根本的なメンタリティが違い、昇華には、至らない
もっと周知していれば、もう少し違った形になったのではないかと思いますが、すぐには達成は厳しく、いわゆる万博のレガシーをどのように引き継ぎ、活用するかによって変わると思いました。
今のままでは、困難だと考えます。温暖化対策は、2050年達成困難。私たち一人ひとりの省エネに取り組むべきです。私たちの課題は、来期雄々しく立ち上がる予定です。年代の枠から学校の枠などを跳び越え、未来のための環境塾に挑戦します。応援お願いします。
Love&Peceの歌を歌い平和と人権の大切さを実感して貰う、その先愛と平和の大切さを歌を通して活動しエクステンションしていきます。
意識高い人はほんの1~2割程度に感じる。多くの方々は日々の生活が精一杯だったり、そもそも環境意識自体に興味関心がない。社会全体が興味関心を持ち、行動しなければ達成出来ない。日本の場合、SDGs教育を受けた若年層よりも高齢者層の方が理解されていないし、関心自体ないように思う。
日本人だけの目標なら、縄文時代に戻った生活をすれば達成できるのだろうが。笑そもそも、資本主義経済とSDGsは大きな矛盾、逆ベクトルを持たざるを得ない物なのに、両立させるには相当のシフトチェンジ、ゲームチェンジャーが現れない限り達成できないのでは?現代の革新的技術は1秒1秒づつ進化し続けている。AI、ナノテクノロジー、ゲノム、オートメーションロボティクス、ヒューマノイド、量子力学などは、2030年には更にステージが上がっているだろう。そして、我々人間は、1秒1秒で腹が減る。食べて飲まなければ生きていけない。第一次産業(農産物、水産物、鉱物)という、地球の天然から搾取、狩猟、採掘が更に進んでる現状をSDGsとテクノロジーが、どのように整合させるのか、それが全人類に伝わらなければ、これらのハイテクに寄って新たな問題が勃発するのは目に見えてる。というやや悲観的な思いです。
考え方は定着するであろう。
プログラム③「新たな時代の万博とテーマウィーク」



【プログラム概要】
以下リンクよりご確認いただけます。
→新たな時代の万博とテーマウィーク | 大阪・関西万博テーマウィーク
【参加感想】
・万博におけるテーマウィークの意義は何か?大阪関西万博のテーマウィークから未来につながるレガシーは?
次世代への”いのち”の繋ぎ方、引継ぎ法を全世界の各国の国民が一人一人考え直して、Quick speedではなく、自然の摂理に応じた、Slow speedに委ねて、整然過程の食産物の有り方から自然の形状流通を見直す事で廃棄量の減少に繋がるでしょうし、高品質化の無駄も抑制される。
テーマウイークより 地域コミュニティ 教育委員会社会教育 で学び合いをユネスコの生涯学習ですべきではないかやったフリだった
いろんな国が一堂に集まるイベントは世界平和実現のために重要。みんなが知恵を披露しあうテーマウィークの意義は大きい。
宮田氏の今回の万博成功したことで「多様な未来は 自分の未来を考えるきっかけに」というフィードバックを得たという。7つの各提言の根元にある「共創」ということが大阪関西万博のレガシーではないかと思い このレガシーが次回開催リヤドへそして その先の未来の国際イベントに引き継がれて行くことを願望する。
最新技術の建物や未来に向けた展示や技術と共に、静けさの森や各国の歴史や慣習の展示やメッセージ発信は、これからの未来、地球規模のSDGsやBeyondを考える良い機会となった。
大阪2025はSDGs-Beyond万博であるとのこと。SDGsとその先にナニが出てくるのか・・・結構難しい。「8つの地球的課題」を設定し、テーマ館は当然のこと、日本企業や各国のパビリオン、そして今回のテーマウイークスタジオでも「テーマウイーク」として取り組んでいる。Dr.Tarekのハナシは実に面白かった。「テーマウイーク方式」は、前回のDubai2021万博の、その名も「Oppoturnity Pabilion」で始まったとのこと。そこには多くの国の多くの階層の人々が集まり、そのテーマの課題を共通認識しいろいろなソリューションが提案なされたとのこと。Dubai2021のソフトレガシーとしての「テーマウイーク」方式であるが、大阪2025ではまだ「ing」であり、リヤド2030に期待したいとのことであった。SDGs-Beyondに取り組む難しい課題であっても、多くの人々の対話とコラボレーションにて、ソリューションが間違いなく見えて来る・・・「Mission Possible」・・・これはイイね。ところで、テーマウイークスタジオの場所がねえ・・・道順が判りにくい奥まった場所で、ナンでメインの場所に設置出来なかったんかね・・・
万博は「地球規模の課題解決」を形式的に取り組むべきではないと思う。展示には グリーンウォッシュやオランダの誤謬のようなものが多く見受けられた。本気でやるなら 見せかけだけの共創ではなく、実質的な共創の場としてレガシーとして欲しい。万博で「地球規模の課題解決」としてテーマウィークをするなら会場のメインの通り道でしたり、パビリオンの待機列の人が話を聞けるようにディスプレイやスピーカーを置くなど、いくらでも工夫はできた。ネット経由でチャットで参加してもらうこともできた。 そこまでやらなかったという事が 万博が宣伝のために「地球規模の課題解決」と言ってみせる。つまりグリーンウォッシュの元凶のようなことをしているように感じた。
ドバイ万博から大阪万博に引き継がれたテーマウィークの考えは万博を訪れる人々やステークホルダー全てにとって万博の理念をより深く理解し、自らの行動をつなぎ合わせる上で非常に有効だと感じた。文化や価値観の異なる国を転々とする万博である一方でリヤド万博にもこの考え方は引き継がれるとのことだったので期待を持っている。
テーマウィークの内容は、素晴らしいが一般客も含めて発信力が欠けた印象がある。
テーマウィークの意義は、“出会いと共創”だと認識しています。異なる立場の人々が一緒に未来を考え、行動のきっかけをつくること。そして、万博後もそのつながりが続いていくことこそ、最大のレガシーだと感じています。
・万博におけるテーマウィークの意義は、各パビリオンにおいて向き合う課題と対策・解決策を発信し、対話や情報共有することで、1つの地球が持続可能なより良い未来へ向かうために必要不可欠な取り組みであることを再認識しました。・未来につながるレガシーは、大阪・関西万博からリアド万博へと、多様な価値観や異なる視点で世代間を超えて脈々(ミャクミャク)と受け継がれるソフトレガシーの創出だと思います。
テーマウィークは地球規模の課題に対する意識を高め、具体的な行動を促す取り組みであることから産学官民・国際機関・市民が協働し新たな価値を生む「実験場」。 知識・ネットワーク・価値観・行動様式を未来社会に継承していくことでしょう
テーマウィークは、政治・学術・市民・ビジネスといった多様な主体が一堂に会し、課題とストーリーを交差させる貴重な場だと感じました。ドバイが示したように、万博は単なる展示イベントではなく、社会的・経済的な対話の「橋」を築くプラットフォームとして機能し得ます。大阪・関西万博では、このテーマウィークを単発イベントで終わらせず、対話と交流を継続的な仕組みへと転換し、未来の都市・産業・コミュニティ形成に向けた実効的なレガシーとして位置付けていく視点が鍵になると思いました。
大屋根リングとシグネチャーパビリオンの数々が「多様でありながらつながっている」ことの重要性を具現化していました。多様であり続けるために、またつながり続けるために、私たちはどう考え行動すればいいのかについて、真剣に考える機会が、テーマウイークだったと思います。未来につながるレガシーは「多くの課題について正解があるわけではない。多様でありながらつながっていくこと、絶えず意思の疎通を図り交流を続けることがよりよい社会につながるはず」ということを多くの人によって確認したことだと思います。
他者の考えを知って、自分の考えを考える?知ることだと思います。問い、投げかけ、興味、好奇心。好奇心が、すべてのはじまりだと思っています。
大屋根リングが体現する「一にして全、全にして一」が、今後に生きてくるのでは
まずは、未来のことを考える。この考える機会を、どのように残して、活用するかがポイントだと思います。イベント(お祭り)が終って、終わりではないこと、それを有効活用する「仕組み」や組織が必要と感じました。
万博のテーマウィーク良かったと思います。いろいろな人、団体が真面目にそして真摯で良かった。もう少し、おおきなカテゴリーに離合集散も必要かもしれませんが。
地球規模の大きな課題について、多様な人の多様な考え方を聞き自分で解決策を考えること。レガシーは「いのち」。
SDGs2030まであと5年弱、SDGsと言う言葉は浸透しましたが、どう達成するかなど、それまでの過程がハッキリ見えないところがありました。しかし、今回このプログラム、この大阪関西万博を通して、各国、世界の様々な本気のSDGsへの取り組みなどを見ることができ、ゴールまでへの道(Beyond)が垣間見れたような気がします。万博で終わりではなく、今後は更にBeyobを加速させ、レガシーとして受け継がれていければです。
レガシーは1番大事と考え、世界を音楽でつなぎ愛と平和の歌を中心にアーティスト達と一緒に創り上げていき万博からのレガシーとします
「今を創り、未来に繋げる」未来を創るために、今に投資する。投資(攻め)をしなければ、やがて衰退・後退する。国籍関係なく、一人一人地球人。地球人として、この今を生きる事自体がレガシーとなる。
大阪万博(あまり、関東や中部では盛り上がってない?)は、失われた30年の日本の中で最も大きな革命的な出来事だったと思う。まさに世界中から集まって多くの人達が、語り合う場、それは国連レベルから市民団体レベルまで、それぞれの価値観や実践している事や思いを共有して共感できた事で、人類共通の問題であり、日々の生活の中で身近に起きている事だと知ることで、日本でも何か出来ると思えたからです。閉会したからこそ、この後の全ての建造物、パビリオンがどのように再生、再利用、サーキュラーエコノミーの流れに納まるのかを見届ける必要がある。スクラップアンドビルドの流れが、ここでどう変わるのかが、本当のレガシーとして市民に届くのかと。
多様性でありながら1つ、と言うメッセージのもと、8つのテーマで、世界の多様な方々が、それぞれの切り口で同じテーマに対してディスカッションできた事は大変意義深いと感じた。今回の大阪万博によって確認された各テーマの意義進捗状況、これを次の万博に向けて実践を続けていくことが必要であると感じた。また、未来は待つものではなく、今現在の様々な行動を通じて選ぶものであるというというメッセージにも大変共感した。
多様な人たちのつながりで結びつき、機能的に活動できる糸口ができたこと。
大阪・関西万博における「テーマウィーク」の意義は、世界中の人々が共通の課題について一緒に考える貴重な機会を創出することだったと思います。
気候変動、健康、教育、平和など、私たちが直面するグローバルな課題に対して、国や文化の垣根を越えて対話し、アイデアを共有し合える場は、そう多くはありません。テーマウィークでは、さまざまな国が同時にイベントを開催し、異なる視点や価値観が交差します。参加者は自分の考えを深めるだけでなく、他者との違いを知り、共通点を見つけることができます。「対話の場」が生まれることこそが、万博の大きな魅力であり、テーマウィークの本質的な価値だと感じました。また、テーマウィークの枠組みは、ドバイ万博から引き継がれたレガシーでもあります。この仕組みを大阪・関西万博でも継続し、さらに発展させていくことは、未来の万博にとっても重要な意味を持つでしょう。世界中の人々が共に考え、共に動くきっかけとなるテーマウィークは、万博の中でも特に持続可能な価値を持つ取り組みだと思います。こんなにも多様な国や人々が、同じ時間に同じテーマでつながるイベントは、世界でも他に類を見ません。だからこそ、このテーマウィークという仕組みを今後も大切にし、未来の万博へと引き継いでいってほしいと願っています。