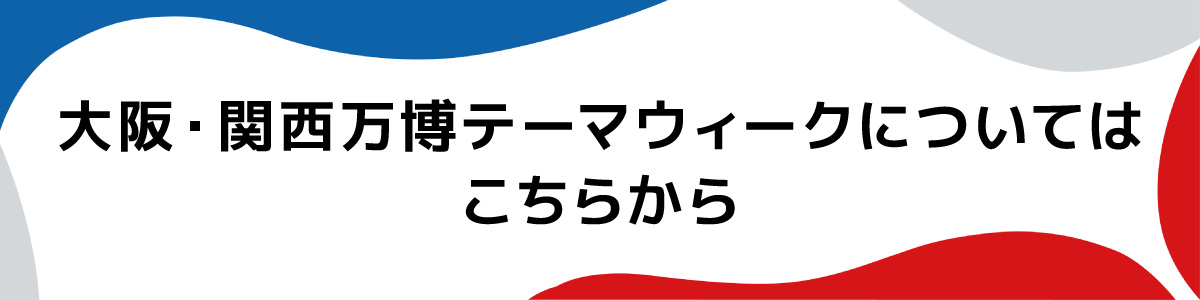公益社団法人2025年日本国際博覧会協会とアジア太平洋トレードセンター株式会社は、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)のテーマウィークの実施に向け、連携協力を行っています。
本WEBページにて、テーマウィークの情報発信を行ってまいります。
9月19日開催のアジェンダ2025 主催プログラムに参加してまいりました。
・開催場所:大阪・関西万博会場内 テーマウィークスタジオ
プログラム①「自然資本の維持」



【プログラム概要】
以下リンクよりご確認いただけます。
→自然資本の維持 | 大阪・関西万博テーマウィーク
【参加感想】
・「いのち」 の豊かさ (生物多様性) を巡る国際的な議論に、2030年以降を見据え、加えるべき視点/要素は何か
これからは「生物多様性=自然資源」だけでなく、「人間のWell-being」や「公平性」の視点をもっと取り入れてほしいと思います。自然保護が地域住民の生活を圧迫しては意味がないですし、先住民などの知識や文化がどのように守られるか、という点です。また、将来世代への負荷を考える「責任」の視点も課題にすることが大切だと思います。
天然資源を使うことばかりしていると、大気中の汚染などで、健康面や生活環境が脅かされる。各国がそれぞれのできる最大限の資源の再生に力を入れ、もっと再生する質や量を良くしてイカなければならないと思った。
環境への貢献度合いを数値化して示すことの重要性は理解出来たが、この国の95%を占める中小零細企業にとって、大企業のようなレポートにまとめることはきわめて難しい状況です。研究者や大企業が出すデータから、零細企業や一般家庭でも簡単に取り入れられるような簡易的な算定基準(電気代を1000円節約出来たら二酸化炭素削減量はこれくらい、水道使用量が1kl減らせれば環境負荷はこれくらい低減など)といったものを作成し、国の指導(積極的な参加には何らかの特典が必要かと思われる)で普及させていってもらえれば、日本全体で本当に環境問題に取り組むことになると思いました。
2030年以降は保護区を増やすだけでなく、経済システム、都市計画、先端技術、公正な資源配分を包括する枠組みが必要であり、生物多様性を「地球社会の基盤」として、気候、経済、人権を横断する国際ルール作りが重要になってくると思います。
企業として取り組むうえで目的や意義は十分理解できるが、一方で事業で直接影響を与えない業種の場合、取り組み姿勢に大きく影響するため、義務的な要素を加えないと進展はないのではないかと思う。
個々の企業の環境保全への取り組みはよく理解できましたが、企業活動全体として状況が改善に向かっているのか不透明だと感じました。また、森林破壊、海洋汚染、大気中のCO₂増加といった問題は、もはや科学的なエビデンスを待つまでもなく、誰もが直感的・経験的に認識できる事実です。「サイエンスベースのエビデンス」が必要という言葉に違和感を感じました。私たちはすでに十分な証拠を持っており、サイエンスベースの証明を待つよりも、今すぐに行動に移すべき段階だと考えます。大学の研究に頼るだけでなく、私たち一人ひとりが自らの判断で行動を起こすことが、現状を変えるために不可欠だと信じました。また、科学が進化する一方で、科学が真の解決行動を遅らせる原因にもなるとも感じました。
*自然と人間社会の共生:生態系サービス(食料・水・気候調整・文化価値)の重要性を、人間の生活・幸福に直結する形で位置づける。*気候変動との統合的対応:脱炭素と生物多様性保全を一体で進める(例:自然を基盤にした解決策)。*公正性・包摂性:途上国や先住民の権利・知恵を尊重し、国際的な利益配分を考慮する。*世代間倫理:次世代に自然資本を引き継ぐ責任。
後進国に先進国と同様の観点を求めるには先進国からの経済援助や技術支援が必要になるが、先進国自体の体力やアメリカをはじめ自国優先主義が問題になる。国際協調が鍵になると思う。
生物多様性を守るというより、生物は、多様性により生きあっている。
昨今の地球温暖化は科学的に裏付けられたデータの結果であり、今後も各々の行動による意識がより肝要になる事が理解できた。国レベル、地域社会ひいては個人として、一人ひとりが知識や見識を広げ『適切な行動をすれば未来はある』の言葉を信じる必要があることがパネリストの方達からとても力強く感じられた。ミクロな取り組みがいつかマクロな結果になること常に意識して取り組みたい。
大手企業だけでなく、中小企業(市民も含む)も含めた取組が必要と感じている。この層におけるネイチャーポジティブの取組みが活発になるような仕組みを行政側に提供頂きたい。
リソースに限りもあり、2030年以降は気候・生物多様性・汚染の“三重危機”統合、ネイチャーポジティブの定量目標と企業開示(TNFD等)の実装、先住民・地域の権利尊重、遺伝的多様性と土壌・微生物圏の保全、自然資本会計と公正な移行、デジタル監視と倫理を組み込む視点が重要であると考えます。
アナ・マリアさんは「自然資本を保存/再生」するためには、①経済活動の自然資本に対するインパクトを、科学的に透明性で持って分析評価する。②(各国は)自然資本を保存/再生する条約を締結しそれに基づいた政策を行使する。③政策では金融的/経済的メリットを創出する事がこの事業の継続的推進には重要なことである。と、明確な筋立てで説明なさった。これは説得力があり、それを実践なさっている大手企業さん二社の事例報告はグッドであり美しい・・・イイね。ものづくり中小企業において、省エネは自社メリット(補助金もあり)。脱CO2はSCOPEでカウントされて、頑張って貢献している。しかしである、中小企業とって自然資本維持はその次の次であり、自然資本を維持するにはおおいなる資金が必要である。社長のポケットでヤレル企業は・・・これまたイイね・・・で良いのかどうか。森は美しくスピリチャルである、ここは大いにイイね・・・あるが。
科学的根拠に基づく、企業・団体の取り組みについて、話が聞けたのが良かった。もう少し時間があれば、一歩踏み込んで万博開催地での議論が聞きたかった
世界的にあるべき姿の作成。これを元にして色々な議論展開を行うべきです。
最後の質問でも出ていましたが、洗剤全般が気になります。洗濯洗剤は環境への配慮も少しはされていそうですが、トイレやお風呂の強力な洗剤や車を洗う洗剤など、汚れやカビを落とすことが最優先で、流れ出た先の影響がどこまであるのかが気になります。
プログラム②「循環経済の実現」



【プログラム概要】
以下リンクよりご確認いただけます。
→循環経済の実現 | 大阪・関西万博テーマウィーク
【参加感想】
・経済・Well-being・サステナビリティなどのバランスを取りながら豊かな未来を追求するために、”循環経済”の実現を手段とすることは可能か。
簡単ではないと思いますが可能だと思います。岡山の真庭市のくらしの循環センターの液肥を遠心分離にかけるという取組は初めて知り驚きました。企業と政府が協力し政策やインセンティブなどの枠組みを整備し、地域での循環モデルを作ること、技術の革新をすすめることが重要なのだと感じました。
最終的には可能だと思う。日本では今のところ決まったものにしかリサイクル料も払っていないので、少しずつ元々の製品代に加えていく必要がありそうだと思った。そして再生資源が天然資源でできたものより安価でできるようになれば、もっと資源の循環が進んでいくと思う。
議論にもありました、循環の出口(リサイクル品の需要)とコストの負担が課題ですね。もちろん、シェールガスではないですが、市場価格との競争性かててくれば、自ずと使われるのは、レアメタル論とおなじでしよう。また、エネルギーミックスのために、バイオマスは可能性の一つとはおまいますが、エネルギーコスト、安定性からはスケールメリットは必要なので、プロトタイプにはなりにくい事実も伝えたうえで、どうするかの説明があったほうが良かったとおもいます。都市住民の税負担の納得感がないと補助金にはと感じました。分かってての、要求かとおもいましたが。ありがとうございました。
先進自治体・企業・海外からのユニークな事例報告を踏まえ、パネリストの古賀さんの提起された「循環経済の輪の大きさは素材や地域の特性によっても異なるが、小さな輪・大きな輪がともに必要であり、技術の輪を大きくしていくことの大切さとともに、地域住民への循環経済への理解を促す側面から自治体との連携も大変重要である」とのご指摘が深く心に残りました。
サーキュラーエコノミーがもたらす可能性として、再使用、修理、リサイクル、シェアリングなどで原材料の発掘、廃棄を減らして、環境負荷を大幅に低減することができます。長寿設計、部品の分解、再利用を前提とした製品開発をし、リサイクル義務化、税制優遇などで線形経済からの転換を後押しします。企業や自治体が循環システムへ移行するには設備投資や人材育成が必要となる課題もありますが、経済、Well-Being、サステナビリティの3要素を同時に支える「有効な手段」となり、単なるリサイクル強化ではなく、デザイン、政策、インフラ、文化変革を一体で進める包括的な戦略が必要です。
循環経済に関する価値観の変容が重要である。資源循環に関わる性能に価値を見出し、多くの人々や企業の共通認識として高く評価するエコシステムが必要。ルールや義務化も移行段階では必要なツールであるが、できることであれば、ソフトパワー、そこに共感や快感を自然に感じるような社会感覚が広がれば、循環経済の実現の可能性がもっと高くなると思います。
限りある資源を有効活用しなければならない重要性は理解できているつもりではあるが、実生活で商品を購入するときにはリサイクル原料を使用している商品かどうかといった循環経済の視点ではなく、商品そのものの機能や値段で購入の可否を判断してしまっています。循環経済が推進されない原因には技術的な問題もありますが、経済負担を強いられることに対する抵抗感が最も大きいのではと感じます。地球上で暮らす私たちは温暖化など差し迫った脅威が存在することを理解し、豊かな未来の追及のために循環経済の費用負担に対してある程度は受容していく意識の醸成が求められていると感じました。
可能性あり:循環経済は「資源効率」「廃棄物削減」「再利用」で環境負荷を減らしつつ、新たな産業・雇用を創出できる。*Well-beingとの関係:モノの大量消費ではなく、サービスや体験価値にシフトすることで幸福度を高められる。*課題:制度設計(規制・税制)やグローバル・サプライチェーンでの公平性を担保する必要。*結論:循環経済は持続可能な未来への重要な手段の一つ。
循環型経済の実現は必須になるが登壇者のインドはリサイクル率20%とあるように各国の現状も違う。循環型経済にはコスト増になることで実現が困難な状況になるので技術開発・生産性向上など課題解決が大切だと感じた。
環境省、自治体、マテリアルを扱う企業、世界的なネットワークを創造する企業、地域での循環の試行と実施を行う研究者という異なる立場の方からの事例や考え方を聞くのが大変興味深かったです。循環型社会の実現に向けては、地域での目に見える循環と、グローバルな仕組みづくりの両方が大切であることが、いまさらながらよくわかりました。特に、三菱マテリアルさんが構築されたPMP LOOP(Product-Material-Productの循環)をREMINEというブランドとして、リーディングカンパニーに提供されているてんは、日本の価値を高めるうえでも大変有意義な取り組みであると思いました。
今の経済秩序より、質素に生きる。自然との共生を考えること。
可能。スウェーデンなどの先進国の事例(デカップリング)がある。先進国の取組も参考にしながら日本流の手段で実現できると考えるし、実現しなければならない。
循環経済は資源効率化や再設計・再利用を通じ、環境負荷を低減しつつ新たな雇用・価値創出を促進します。適切な規制設計、インセンティブ、ステークホルダー協働が鍵で、Well-being向上とも両立し得る。自分自身の生活スタイル・考え方を変革することで、身の周りの省エネ化ができると考えます。
一連の関わる企業のコラボが必要。実現プランパターアンを作成し、そこに関連する企業をセットして、コラボレーションで具体的につなげていく組織があっても良いかと思います。
ここ数年アフリカに通っていますが、行き場を失くしたごみの量がすごいです。医療廃棄物の処理もJICAの現場の方からも深刻であることをお聞きするなど、経済の発展を最優先させたままでは、とてもではないけれど、循環型経済への移行は難しいのではないかと思えてきます。well-beingとサステナビリティが大切で、そのためには経済に関しての抑制がなければ、難しい。
プログラム③「気候変動への対応」



【プログラム概要】
以下リンクよりご確認いただけます。
→気候変動への対応 | 大阪・関西万博テーマウィーク
【参加感想】
・2025年現在、気候変動が顕在化してきていると言われる中、改めて、今私たちが考えるべきアジェンダは何か。
少しずつ浸透してはいますが、やはり消費の「買う・捨てる」から「使う・直す・共有する」といったスタイルに見直すこと、地方・地域レベルでの循環エネルギーや廃棄物の処理、サステナビリティに関するさらなる情報発信、また国際協力も必要であることを再確認しました。
決して歩みを止めず再生できるものは再生できるように開発していき、それを好んで買う人が増えていくこと。各人が買う物をよく考えて買う、例えば日本では包装も大変丁寧にしているが、必要のない包装は望まない、長持ちする物を買うなどだけでも変わっていくと思う。
今回の万博でも多く紹介されているように、温室効果ガスの排出抑制や回収に関して、技術的には相当可能となっています。しかし、主に経済性の観点から、普及がなかなか進みません。普及方策の検討及び実施について、幅広く議論がされることが強くかつ早急に待たれます。
登壇者皆様が、真剣に考えられていることがよく伝わってきました。気候変動に対応する方法等を考えるのは、特別に大きな発想の対応だけではなく、一市民レベルの小さいけど着実な実施が大事だということに気づきました。参加してよかったです。
2025年のアジェンダは緩和(排出削減)、帝王、公正な移行を同時に進めることであり、温室効果ガス削減だけでなく、気候被害への備え、生活、経済システムの構造転換、誰も取り残されない仕組み等、これらを統合した包括的な戦略を描くことが今まさに考えるべきテーマと言えます。
適応策の強化:極端気象・災害リスクへのレジリエンス強化(都市インフラ、食料安全保障)。*公正な移行(Just Transition):化石燃料依存から移行する際の労働者・地域への支援。* 自然との統合的解決:森林保全、ブルーカーボン(海洋・湿地)活用。*国際協力の深化:排出削減・技術移転・資金支援を通じた先進国と途上国の信頼構築。*行動の加速:2050年カーボンニュートラル目標を前倒しする取り組み。
人権・多様性・意欲を尊重し、安全で活気に満ちた社会を目指して、環境課題に積極的に取り組んでいかなければならない。もちろん、各国・各地域の文化や慣習を尊重して。
近年の温暖化、異常気象と肌で感じるようになり、抑制のための省エネや脱炭素の必要性が顕著になってきている。エネルギー問題も化石燃料代替えの太陽光、水力、風力、地熱等再エネの推進に加え原子力や新な技術開発も必要になる。国際的な課題でもあり、人類が知恵を出し解決していかなければならない。
気候変動対策は安全保障と幸せ追求を目的としシナジーを生みリスクを低減させるものという見宮先生、ハウスマン先生の自然(太陽と風の力)をマネタイズするというお話に共感しました。また、大場先生の蓄電池よりもお湯の方がエネルギー効率が良いが現実的なイメージやわかりやすさ優先で蓄電池が採用されていることが現状を象徴しているように思います。緑に携わる人間としてグリーンインフラの提案やあり方そのものも今回学んだ方向へ進めるべきだと理解しました。経済合理性の追求という事だけにとらわれず緑の力をもっと簡単に共感してもらえるよう活動していこうと思います。
食と農の在り方を、見直しまず無駄をなくす。
日本には大学や研究機関、企業における技術力があるが、市民における環境意識がまだまだ低いと考えている。産官学が連携協力し、市民への啓発活動をさらに加速すべきと考えている。
気候変動適応と緩和の両輪が急務と考えます。脱炭素(再エネ・省エネ・産業転換)、レジリエンス強化(防災・インフラ・健康)、公正な移行(雇用・地域格差)、自然資本保全(生物多様性)、資金動員と透明な開示、国際協力・技術移転を統合的に進めることが重要と考えます。
世界各国が気候変動を喰いとめる必要性と危機感を持つためのアクションプラン、ビジョンあっての展開世界的にベクトル合わせを行っての行動が必要です。個々の利益追求での判断を変えていく為の世界的な行動。
自分たちそれぞれが真剣に取り組むことが必要。できることをやるという簡単なことだけでは取り返しのつかないことになるのではないかと思います。構造的な転換というより、思考を変え、思想の転換が必要な気がします。
地球は一つであり、国境は人間が勝手に引いたものに過ぎない。また歴史の中で常に書き換えられている。一つの地球の環境バランスを保護するには大国、小国関わらず向き合わなければならない。変動防止コストを誰が払うのではなく、地球人として自身が住む環境保護は一人ひとりが向き合うべきである。人間はそれができると思っている。
次回の10月12日(日)も、大阪・関西万博のテーマウィークプログラムに参加します。
□8人のテーマ事業プロデューサーと考える“いのち”とSDGs+Beyond
□「いのち輝く未来社会」のデザインに向けた提言
□新たな時代の万博とテーマウィーク
□8人のテーマ事業プロデューサーと考える“いのち”とSDGs+Beyond
□「いのち輝く未来社会」のデザインに向けた提言
□新たな時代の万博とテーマウィーク