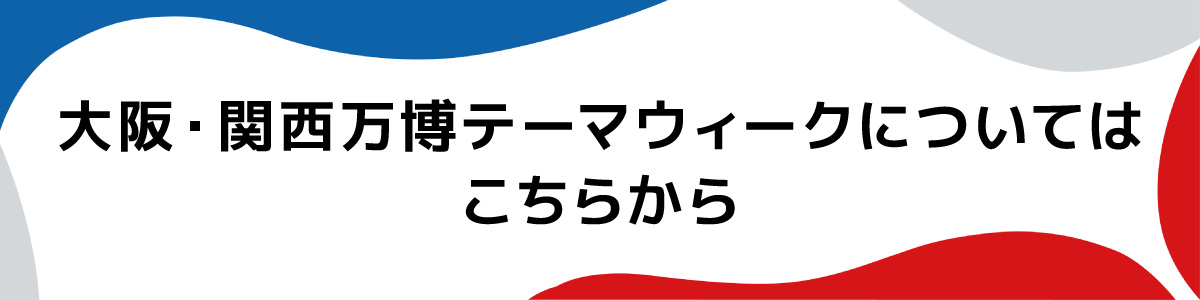公益社団法人2025年日本国際博覧会協会とアジア太平洋トレードセンター株式会社は、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)のテーマウィークの実施に向け、連携協力を行っています。
本WEBページにて、テーマウィークの情報発信を行ってまいります。
8月12日開催のアジェンダ2025 主催プログラムに参加してまいりました。
・開催場所:大阪・関西万博会場内 テーマウィークスタジオ
プログラム①「人権を尊重・保障されるために、今我々が考えるべきことは何か。」



【プログラム概要】
以下リンクよりご確認いただけます。
→人権の尊重・保障 | 大阪・関西万博テーマウィーク
【参加感想】
・人権を尊重・保障されるために、今我々が考えるべきことは何か。
被爆80年を迎えた節目の夏。平和、人間の安全保障、人権の過去・現在・未来を考える素晴らしい内容だった。特に、金本さんと近藤さんの被爆体験が胸に迫った。当時のことを話されながら涙される姿に、今も戦われていることを感じた。これまで戦い続けてこられているのに、あと20歳若かったら、もっと平和のために動けるのにと語られている姿に心が打たれた。かつて私も広島に住んでいたことがあり、平和について考え、行動した。広島を離れて10数年。今日の登壇者の方々のように、平和への行動をそれぞれの立場で、それぞれのやり方で続けておられる話を聞き、忘れていたものを思い出した気持ちになった。平和な世界に向けて、一人一人にできることがある。また、核兵器廃絶を自分事として捉え、できることから始めたい。まずは、身近な人に親切にすることから。平和を考えていきたい。素晴らしいプログラムに参加できて本当に良かった。ありがとうございました。
広島の被爆者が、登壇され体験談を聴講しました。被爆者の平均年齢が86歳となり、風化しない様に若い世代の人に伝え続ける事が重要。ソマリアの人がonlineで「教育は平和を守る武器」と云われ感銘しました。
金本さん、近藤さんという被爆者の方の生の声を聞くことは初めてでした。辛い過去のことをこれまで何度もお話しをされてきたと思いますが、それでも時に声を詰まらせ、手を振るわせながら、お話しされている様子から、伝わってくるものがありました。世界での紛争が増えています。私も1~2月にウガンダ、ブルンジ行っていましたが、コンゴの内戦が激化し、コンゴからの難民が越境されてくること身近で感じました。なぜ争いは無くならないのか。フォーラムの最後のメッセージとして、一人一人が平和について、核廃絶について何ができるか考え、団結することで、この難局クリアしていくことができるという力強いメッセージに、今一度、自分自身の足元を見つめ直し、考え行動していきたいと思います。すばらしい機会をいただきましてありがとうございました。
戦争や核兵器の問題が、過去ではなく今も続く課題だと強く感じました。「憎むべきは人ではなく戦争」という言葉や、被爆者の方々の語り継ぐ姿に心を打たれました。「自分は今日何をしたらいいのか」という問いかけを胸に、日常の中で平和のためにできる行動を積み重ねていきたいと思いました。
平和のためには原爆を含む戦争の記憶をつないでいくことが必要であるが、特に被爆者も高齢化しており、手段として映画等の手段が有効であると認識しました。過去、現在、未来のための記憶の意味を考えさせられました。また金本様、近藤様のお話は心に刺さりました。
「2100年がどうなっているのか」現状の延長線から明るい未来を描くのは難しいと思います。先の大戦から80年経っても人類は何も学んでいないと悲観的にならざるを得ません。あきらめず、今回のパネラーの方々のお話を自分自身の考えの中に落とし込んで周囲の人たちに影響を与える存在になりたいと思いました。
原爆被爆者の生の声を聴けたことが非常に有意義でありました。
今回は、人権の尊重と保証というテーマで、被団協(被爆者)の方から直接お話を伺い、平和の大切さ、常に意識を強く持つことの重要性を感じました。私は、被爆者の方は、自らの権利侵害を訴えられているものと勘違いしていた部分もあったのですが、全くそうではなく、自分たちは被害者ではなく、他の亡くなった方々、助けを求める人たちを救うことができなかったという罪悪感を常に感じながら、生きてこられていたという話、憎むべきは人ではなく、戦争そのものであるという話、そして、その記憶を記録として残し、語り継ぐことで、地球市民一人ひとりが、悲惨な過去を二度と繰り返さないという決意を持って欲しいとの訴えが、心に刺さりました。また、軍縮とは単に軍事費を削減しようという話ではなく、武力に変わる選択肢を考えようという話であること、人権は贅沢品ではなく、人間一人ひとりが生まれながらに持っているモノであること、人権と、人道の違い、そして多くの戦争の根本的要因が、根深い差別や人権侵害に起因していることなど、新たな発見・気づきがたくさんありました。一人ひとりが、朝起きて、今日は平和か?と毎日問い続けることだけでも、世界は変わっていく。自分ができることを考えて、実際に行動することの重要性を改めて感じました。また、今回は、国家と個人の話が中心でしたが、民間企業としてはどのように取り組むべきなのか、という視点も改めて考えたいと思いました。今後は、頭で理解するだけでなく、心で感じ、熱意を持って行動に移していきたいと思います。今回はこのような貴重な機会を頂き、ありがとうございました。
「人間の安全保障なくして平和なし、平和なくして人間の安全保障なし」中満氏の進行のもと、金本氏、近藤氏からのお話とパネリストの皆様のコメントを通して、改めて戦争や核兵器がいかに長期的な悲しみと痛みをもたらすか、考えさせられる時間となりました。深い悲しみとともに、共有くださったバトンを未来につないでいけるように、平和について思いを馳せる機会・企画を自分でも作っていこうと思います。パネリストお一人お一人から、多くの気づきと学びをいただきました。ありがとうございました。
被爆者の方からの話が聞けるとは思っていませんでした。原爆を落とした米兵の方の「神よ私はなんということをしてしまったんだ」。人間が作り出した戦争が人間を苦しめる。そのようなことが二度とないように自分が何ができるかを考えたいと思いました。以前はSDGsを会社で担当しておりました。今は環境のみになりましたが、平和が守られるためにできることを考えたいです。
プログラム②「平和の構築に向け我々が実現すべきことは何か。」



【プログラム概要】
以下リンクよりご確認いただけます。
→平和の構築・実現 | 大阪・関西万博テーマウィーク
【参加感想】
・平和の構築に向け我々が実現すべきことは何か。
4名のパネリストの方々は、生い立ちや現在の活動が全く異なり、それぞれの考え方も多岐にわたっていました。しかし、平和の構築・実現に対する考え方の本質は同じであると感じました。人は生まれたとき、平和を望む心しか持っていません。その後、育った環境や利益、損得勘定が複雑に絡み合い、対立が生まれてしまうのです。個人でも、あるいは国と国との間でも、この対立を乗り越えるためには、まず相手に歩み寄ることが不可欠です。相手との違いを認め合い、共通の目的を見つけ出し、互いに同調していくこと。このプロセスを通して、それぞれの価値観をすり合わせることが、平和な社会を築くために最も重要なことだと考えます。
8人がリンゴの絵を描いても、それぞれ同じ絵はなく異なります。故、平和は一人一人が連携し、大きな輪を作り、その平和は人間のみ作る事が出来る。
万博会場で世界平和を考えることは、それぞれの国の立場で考えることであることをあらためて、思いました。
平和に向けた社会を構築していくには多様性を認め合う、何か芸術にも近い側面があることを知ることができました。平和に向けた活動に関連する商品を知って、購入することを通じ、様々な境遇にある人を応援するきっかけにつなげていきたいと感じました。
蟹江先生の進行のもと、多様な背景のパネリストのみなさんのお話を興味深く聴きました。シリア出身のタレク氏、アフガニスタンのパシュタナ氏の発言「平和とは、水と教育と安全が保証された状態」にドキリとしました。日本では、水も教育も安全も当たり前のこととして享受しています。まずは柔軟な認識が必要です。世界中で起こっている戦争や紛争を、どのように平和な状態にできるのかについては、大井氏、日比野氏の言葉に鍵があると思いました。大井氏「JICA は国連協力機構であって、支援機構ではない。パートナーシップで事業を進めていく」日比野氏「100人の人がリンゴの絵を書いたら、一つとして同じものはなく、100通りの絵ができあがる。その違いは個性や特徴であり、それらを受け入れるのがアートの力」個性(考え方や表現、手段の違い)を受け入れつつパートナーシップで進んでいく。という認識こそ、平和の構築に必要なのだと改めて感じました。
平和の維持。持続的社会への強い欲求。一人ひとりが相手がたへの敬意と尊重 新市場は、まだまだ未開拓と考えるべき。人々の個性的な発想を。教育機会の平等。学びなおし。
本セミナーにおいて、パネリストから示唆に富んだ考えが述べられ、それらが世界に生じているあらゆる課題に共通しているワードだと感じた。その中で、相互理解を得るための傾聴であったり、理解できないことでも受け入れる許容が鍵となるのではないか。過度な尊厳、繁栄、価値の欲求が争いを生む。アートも人間が片付けをすると欲求を生む。個人個人が、許しや知足といった視座を意識することが肝要と考える。
個人の個性の尊重と、共創基盤をどう作っていくか。「アートは同じりんごを描いても同じ絵にはならない」一人ひとりのらしさを大切にするアートの視点は、平和の構築に向けて様々な示唆を与えてくれるということは自分にとってはキーファインディングでした。それぞれのお立場からご経験やご意見をお話くださったご登壇者の方々、企画など携わられた皆様に感謝いたします。
今回のディスカッションを通じて改めて感じたのは、平和が単一のゴールではなく、多面的な要素から成る複雑なプロセスであるという点です。国際紛争の回避といったマクロな視点から、日常の人間関係における対立解消というミクロな視点まで、その射程は非常に広い。そして、それぞれのレベルで求められるアプローチや解決策が全く異なるため、包括的に捉えることの難しさを痛感しました。特に印象的だったのは、パシュタナさんのお話しの中の経済格差や男女の違いによる教育の機会不平等といった、直接的な暴力ではないものの、人々の心に不和を生む根本原因に光が当てられたことです。これらの課題は、表面的な対話や協定だけでは解決できず、社会構造そのものへの深い理解と変革への長期的なコミットメントが求められます。実現に向けた「当事者意識」の重要性議論の中で何度も浮上したのが、「当事者意識」の重要性です。平和の実現は、一部のリーダーや国際機関に任せるものではなく、私たち一人ひとりの行動にかかっているという認識です。職場でのチームワークを円滑にすること、多様な意見を持つ人々と対話すること、そして自分自身の偏見や無意識のバイアスに向き合うこと。これらは一見、壮大な「平和」とは無縁に思えますが、私自身、社会全体の調和を築くための小さな一歩ではないかと考えさせられました。今回のディスカッションは、平和の実現を「遠い理想」として傍観するのではなく、「身近な行動」として捉え直すきっかけとなりました。自分自身が所属するコミュニティや組織の中で、どのようにすればより良い関係性を築けるのか。この問いに具体的に向き合うことが、社会人として平和構築に貢献する第一歩なのだと感じています。最後に、今回のディスカッションそのものが、平和構築の一つの実践だったと言えるでしょう。異なるバックグラウンドを持つ人々が、共通のテーマについて互いの意見を尊重し、耳を傾けることで、新しい視点や気づきが生まれました。これは、対立や分断を乗り越えるために不可欠な「建設的な対話」の力を象徴しています。結論を急ぐのではなく、プロセスを重視し、多様な声を拾い上げる姿勢こそが、より強固で持続可能な平和へと繋がる鍵だと確信しました。今回の経験を活かし、日常の業務や人間関係の中で、より平和的な環境を築くための行動を意識していきたいと考えています。
あらゆる属性や背景を越えて人々が交わる現代において、相手を理解することへの限界を感じることがあります。そんな中、本セッションは「平和とは何か?」という原点に立ち返るきっかけとなりました。特に日比野氏の「アートはわからないことを引き受ける。ほとんどの人がわからない。」という言葉は、理解できないことも肯定してよいという、自分にはなかった新たな視点として深く印象に残りました。
共生、創成の為に必要な事につき、考えさせられる議事でした。ただ、既存の世界・地域・生活に参加するにあたって、その参加される地域側の公正さは、もちろん必要であるが、参加する側のモラルも非常に重要であって、日本で言う「郷に入っては郷に従う」という意識が、必要であると、近々は感じつつある。本来異質であるものを、そのままで受け入れる事には無理がある。それは、受け入れる側の責任ではない
りんごの描き方が1人1人違うように、1つの出来事に対しても多様な視点が存在する。平和の構築に向けては、その多様な視点に対し、相互理解を行っていくことが、重要である。
プログラム③「労働市場による格差是正のためにどのような施策が必要か。」



【プログラム概要】
以下リンクよりご確認いただけます。
→労働市場における格差是正 | 大阪・関西万博テーマウィーク
【参加感想】
・労働市場による格差是正のためにどのような施策が必要か。
賃金的な貧困だけではなく、敎育、健康、インフラ環境などのトータルな意味合いでの貧困への解決に向けて、世代対世代ではなく、世代間の交流、協力したアプローチが大切である。また、企業としてはサプライチェーンと協働して、市場全体で格差是正を進めていく方針、施策が必要である。
人権尊重と多様性推進の具体事例を通じて、国家、企業、市民が協力して貧困削減と持続可能な未来を築く重要性を改めて実感しました。また、人権、企業の責任、SDGsのつながりを多角的に捉えた議論から、多くの学びを得ることができました。特に、人権尊重、多様性を受け入れ誰もが社会に参加できる仕組みづくり、貧困の多次元性、そして社会全体での協力の重要性といった論点には、大きな感銘を受けました。これらの課題解決には、政府、企業、そして個人が協調し、それぞれの役割を果たすことが不可欠です。この協力を通じて、より良い未来への希望が広がると感じています。
格差是正も平和構築と同じ構造のように思う。通訳を通してなので、誤認しているかもしれないが、フェリペが現場の意見を吸い上げることの重要性を訴えていたこと、学生からの現状の悩みに対するパネリストの回答に少し溝があるように感じた。格差是正の一端には優位環境にいる立場から、あえて不利益な位置に下がっていくことと同義のこともあり、万人が受け入れることは難しく特に企業は自組織が壊滅するほどの許容はないので、業績不振になれば人員整理をする。ステークホルダーもそれを是とする。今回のパネリストからは、施策として、諦めずチャレンジし続けるというメッセージと受け止めた。
対話の機会を年長者、若者でもつこと。組織でも対話の機会を作ることで、1人1人の可能性を発揮させる環境を作ること。1人1人の能力を認めることが大事になってくる。待ちの姿勢ではなく、積極的に取り組む必要がある。
若者や女性へ寄り添った様々な施策は、単に企業や当事者だけの問題ではなくどの国にも共通する国の発展のためには欠かせない重要なことであり、国際問題であるということは私には今までに無かった視点でした。当事者である自分から、こういった施策に対して意見することは甘えや我儘だと受け取られるのではと思うことがありましたが、視野を広く持ちながら意見していくべきだと考え方が変わりました。この先AIに仕事を取られてしまうのではないかという点に対し、その時には今は無い職業が生まれているだろうと述べられていたことにとても納得しました。私の現在の職業はAIに取られる職だと言われていますが、今の職種に捉われずに自分の可能性を信じていれば先は明るいのかもしれません。
誰がターゲットか難しい課題への取組、パッションが必要であること。信頼の欠如(社会、政府etc)。何事も戦略が大事であると感じた。最後にサステナブル関連テーマでありながら会場のエアコンが暑がりの私でも寒過ぎました。